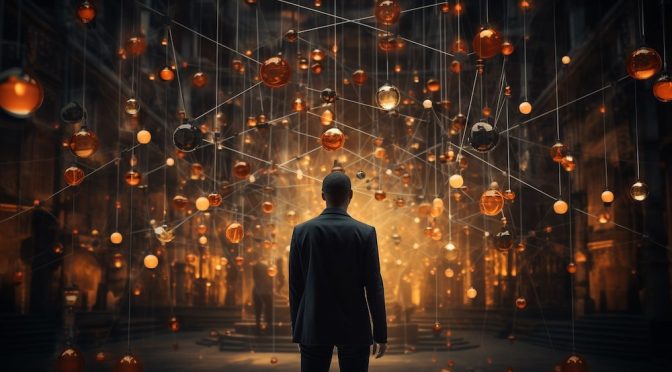皆さんは、食品を購入する際、包装にどれくらい注目していますか? 味や価格、見た目は気にしても、包装まではあまり意識しないという人も多いのではないでしょうか。
でも実は、その包装の選び方一つで、地球環境への影響は大きく変わってくるのです。プラスチックごみによる汚染、食品ロスの増大。その根源には、私たちの何気ない選択もあります。
食品包装は、食べ終わった後も、リサイクルや分解の過程で環境に関わり続けます。だからこそ、購入時の一つ一つの判断が重要なのです。
少し意識を変えるだけで、誰もが地球に優しい選択ができる。そんなヒントを、この記事では提案していきます。
身近なところから、サステナブルな生活を始めてみませんか? 小さな選択の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出す。その第一歩を、一緒に踏み出していきましょう!
食品包装が地球に与える影響を知る
プラスチック問題の実態
食品包装と言えば、真っ先に思い浮かぶのがプラスチック。利便性が高い反面、環境汚染の原因にもなっているのはご存知の通りです。
世界全体のプラスチック生産量は年間約4億トン。そのうち包装材が占める割合は、なんと40%以上にもなります1。その多くは使い捨てで、適切に処理されないまま自然界に放出されているのが現状です。
海洋プラスチックごみの量は、2050年までに魚の量を上回ると予測されています2。微細化したマイクロプラスチックは、私たちの食卓にも忍び寄っています。
自然の中に残り続けるプラスチック。その出発点の多くが、私たちの日常に潜んでいるのです。
食品ロスと包装の関係
食品ロスも、包装と深く関わる問題です。日本では年間612万トンの食品が廃棄されており3、その約半分が家庭から出ているのをご存知でしたか?4
食品ロスの原因の一つに、過剰な包装があります。必要以上に個包装されていたり、大きすぎる容器に入っていたりすると、使い切れずに廃棄につながってしまうのです。
また、鮮度保持や破損防止のために過剰な包装が施されることもあります。見栄えは良くても、中身を守りすぎるあまり、かえって無駄を生んでしまっているのが実情です。
環境負荷を減らす取り組み
こうした問題に対し、企業や自治体での取り組みも始まっています。
「朋和産業」は、プラスチック使用量削減のために、新しい代替素材の研究を進めています。バリア性の高いバイオプラスチックや、紙との複合素材などの採用を検討中です5。
また、環境省は「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制する目標を掲げました6。自治体でも、レジ袋の有料化などを進める動きが広がっています。
企業努力と消費者の意識改革。両輪の取り組みが進むことで、包装の環境負荷は着実に減らせるはずです。私たち一人一人が、食品選びの際に包装にも目を向けること。それが変化の原動力になるのです。
地球に優しい包装素材を選ぶポイント
リサイクルしやすい素材
環境負荷を減らすには、リサイクルしやすい包装素材を選ぶことが大切です。では、具体的にはどんな素材が良いのでしょうか?
まず、紙製の包装は古くから使われてきた定番素材。再生紙を使ったものなら、なおのことエコです。紙パックやダンボールなどがそれに当たります。
次に、ガラスや金属も、リサイクル率の高い素材として知られています。ビールビンや缶詰などは、洗って繰り返し再利用できるのが魅力的。
PETボトルは、プラスチックの中では比較的リサイクルしやすい部類に入ります。ただし、ボトルとキャップは別の素材なので、分別が必要なのは要注意です。
素材選びのポイントは、以下の通り。
- 紙、ガラス、金属など、リサイクルしやすい素材を優先する
- プラスチックなら、PETなどリサイクル可能なものを選ぶ
- 異なる素材が複合しているものは避ける
生分解性素材のメリット・デメリット
近年注目を集めている生分解性プラスチックも、有望な選択肢の一つです。トウモロコシなどの植物由来で、自然環境中で分解される素材のことを指します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・石油資源の節約になる ・自然分解するため、環境汚染のリスクが低い |
・コストが高い ・分解には一定の条件が必要 ・リサイクルには不向き |
生分解性素材は、まだ課題も多いのが正直なところ。でも、技術の進歩とともに、私たちの選択肢は確実に増えつつあります。
再利用可能な容器を選ぶ
使い捨てを避け、再利用可能な容器を選ぶのもおすすめです。最近は、デザイン性の高い詰め替えパックも増えてきました。
ジャムなどの瓶詰めは、空き瓶を食品保存に活用できます。業務スーパーでは、プラスチック容器の回収も行っているそうです。
詰め替え用の大容量サイズを買うのも一案。ディスペンサーなどに移し替えて使えば、ごみの量を大幅に減らせるはず。
再利用の工夫は、身近なところにたくさん転がっているのです。
賢く選ぶ!身近な食品の包装例
スーパーで買えるエコな商品
私も、買い物の度に環境に優しい包装を心がけています。最近のお気に入りをいくつか紹介しますね。
まず、野菜売り場で見つけた「幸せ包み」。新聞紙で包まれていて、見た目も味わい深い。リサイクルにも適しているのが嬉しいポイントです。
調味料コーナーでは、詰め替え用のパックが充実。ノズルが付いていて、そのまま使い切れるタイプが便利だと実感しました。
冷凍食品も、紙パッケージのものを選ぶようにしています。「朋和産業」が手がける商品にも、エコ素材のものが増えてきたように感じます。
外食時の容器選びのヒント
外食や持ち帰りの際も、包装の選び方で差がつきます。ファストフード店の場合、以下のような点に注意しましょう。
- 紙ナプキンは必要な枚数だけ取る
- マイ箸やマイストローを活用する
- 割り箸は、間伐材や竹製のものを選ぶ
フードデリバリーでは、リユース可能な容器を使うお店もあるそうです。注文の際、容器の種類も確認してみると良いかもしれません。
過剰包装を避けるコツ
店頭で過剰包装を避けるには、バラ売りや量り売りを上手に活用しましょう。ばら菓子や米などは、必要な分だけ購入できるのが魅力です。
通販でも、「簡易包装」や「まとめ買い」の選択肢があれば、迷わず選ぶようにしています。ワンランク上の包装にグレードアップするより、シンプルな方が環境に優しいことが多いですからね。
贈答品も、過剰包装の典型。高級感を演出するあまり、中身以上に包装に力が入っていることがよくあります。相手の好みを考えつつ、できるだけ簡易な包装の商品を選ぶのがおすすめです。
私たちができること:小さな選択が未来を変える
日々の買い物での意識
包装選びのヒントを紹介してきましたが、何より大切なのは日々の意識です。一つ一つの選択が、地球の未来を左右すると考えると、気持ちが引き締まります。
「この商品なら、使い終わった後も再利用できそう」
「少し割高でも、エコな素材のものを選ぼう」
買い物の度に、そんな視点を忘れないようにしたいものです。
一人一人の意識の積み重ねが、ゆくゆくは市場を動かす大きな力になる。そう信じて、これからも環境に優しい選択を続けていきたいと思います。
企業へのメッセージ
とはいえ、消費者の選択肢は、企業の取り組み次第でも変わってきます。私たちができることは、商品選びを通じて、企業に変化を促すことです。
お気に入りのメーカーの商品に過剰包装が目立つなら、お客様窓口に意見を伝えてみるのも一案。ささやかな行動でも、企業姿勢を変える一歩になる可能性があります。
環境に優しい包装は、コストが掛かるというイメージもあるかもしれません。でも、将来を見据えた投資だと考えれば、企業にとってもメリットがあるはず。長期的な視点を大切にしてほしいと思います。
自分だけのエコアクション
最後に、一人一人ができるアクションプランを考えてみませんか? 私のおすすめは以下の3つです。
- マイバッグ・マイボトルを常に携帯し、使い捨て包装を減らす
- 詰め替え用や簡易包装の商品を積極的に選ぶ
- SNSなどで、お気に入りのエコ商品を発信し、輪を広げる
小さな習慣の変化が、やがては大きな社会の変化につながっていく。そんな想いを胸に、一歩ずつエシカルな暮らしを実践していきたいものですね。
まとめ
食品包装は、味や鮮度を守るだけでなく、地球環境にも大きな影響を与えます。だからこそ、私たち消費者一人一人の選択が重要なのです。
リサイクルしやすい素材、再利用可能な容器、生分解性のものなど。環境に優しい包装を選ぶためのポイントは、身近なところにたくさんあります。
スーパーや外食で、ちょっと意識を変えるだけで、誰でもエコな選択ができる。そんな工夫を、日々の生活に取り入れていきませんか。
もちろん、企業の協力も欠かせません。過剰包装の削減や、代替素材の開発。消費者の声に耳を傾け、前向きに変革を進めてほしいと願っています。
食品包装を通して、地球に貢献する。難しく考える必要はありません。自分にできることから、少しずつ始めてみるのが一番です。
小さな選択の積み重ねが、いつかは大きな変化を生み出す。そんな希望を胸に、これからも私は、食品包装に思いを馳せ続けたいと思います。